第41話 アグン山制覇

スタート地点の寺院が見えてからというもの、早く帰って眠りたいという気持ちが強くなって、足が自然と前へ前へと進んでいく。
先頭のガイドのおっちゃんは、相変わらず疲労の色を見せることなく、オレとゆうやと、少しずつ遅れ始めたリッキーのことを確認しながら先導している。普段から何度と登頂しているとはいえ、4、50代であろうおっちゃんの体力は驚異的である。
後方のマルセロとタイサはというと、すでに差が開きすぎてどれくらい後方にいるのかはわからないが、もうひとりのガイドがついているので無事であろう。
黙々と進んでいくと、ついに見覚えのある、寺院のすぐそばにある最初のスタートしたときの道へたどり着いた。ゴールは目と鼻の先にある。嬉しくなって、最後の力を振り絞ってオレは走り出せる、と思ったのだが、脚に走れるほどの体力は残っているはずもなく、仲良くおっちゃんとゆうやとオレの3人でゴールした。
「ゴォォーーーール!!」思わずサッカー中継の実況ばりの声で叫んでしまった。オレの雄叫びがこだまする。もしかしたら、マルセロたちにもオレの声が届いて、ゴールはもう少しと知って、やる気になったかもしれない。
とうとうオレたちは成し遂げた。午前1時からスタートして、午前9時半にゴール。8時間半かけてアグン山を制覇した。
だが、達成感よりも断然ねむ気のほうが勝っていた。オレは腰を草原に下ろした、というよりも、膝から崩れ落ちたというほうが正しいだろう。脚はとうに限界に達していた。背負っていたリュックを枕にして、大の字に寝転がって静かに目を閉じた。すぐに意識はどこかへ行ってしまった。
なにやら周りから聞こえる人の声で目が覚めた。視線を声の方へ向けると、隣でマルセロとタイサ、リッキーが話している。彼らも無事にゴールできたみたいだ。
「マルセロ!! タイサ!! リッキー!! やったな!!」
「ユウマ!! また明日登ろうぜ!?」とマルセロが冗談混じりに言う。
「いやいやいやいやいや。もう2度とやらないからな!!」
オレが応えようとしたことを、真剣な顔のリッキーがオレより先に応えたのだった。
時計を見ると10時半になっていた。1時間は寝ていたようだ。少しは体力が回復したが、全身が激痛で言うことを聞かない。
「みんな揃ったし、写真を撮ろう!」マルセロが一声で、ガイドも含めみんが寺院の前に集まった。

ガイドのおっちゃん以外は、空元気の写真。こんなの嘘っぱちだ。
「よし、今の気持ちを現した表情で!」とマルセロが提案した。

疲労困憊!! うん、これでよし。
みんなでガイドのふたりにお礼を言うと、「はっはっはっはっはっは!」と手を振って帰っていった。
オレたちも予約していたタクシーが迎えに来ていたので、駐車場に向うのだが、最後の試練が用意されていた。そんなに長くはないが、階段や坂道を下りなければいけなかった。全員がロボットのようなぎこちない動きで、一歩一歩慎重にゆっくりと下りていって、ようやくタクシーの元へついた。
荷物を車に積んでいるとき、最悪なタイミングで急に便意が催してきた。オレは、気持ちだけは急いでいるのだが、言うことを聞いてくれない体と格闘しながら、ゆっくりと歩きながら近くのトイレに飛び込んだ。
扉を開けて更に衝撃を受けた。なんと、和式トイレのような便器が床に設置されている。歩くことすらままならないこの状況で、さらなる追い打ちをかけられた気分になった。
しゃがもうとするが、さほど膝が曲がらず腰が落ちない。仕方なく、中腰になって少し高めからのうんこを試みた。飛び散らないように慎重に、どうにかこうにかして、無事にうんこを済ませた。バリのトイレは、日本では当たり前のように準備されているトイレットペーパーなどないので、事前に準備していたポケットティッシュできれいにお尻を拭いた。
でなければ、トイレに準備されている水が貯められている大きなタンクから水を手に取り、おしりを手で洗うはめになる。いくら好奇心が旺盛なオレでも、その領域にはまだ踏み込めない。
最後にタンクから桶で水をすくい、勢いよく便器に流してうんこを流す。それがバリの一般的なトイレである。
トイレから出て、みんなが待っているタクシーに乗り込み、やっとのことで帰路へついた。念願の『帰る時間』である。
車は木々に囲まれた山道を下っていく。中途半端に舗装された道の凸凹を拾う車が醸し出す小刻みな振動が心地よい。
振り返ると、約9時間の半端なく過酷な、人生初の本格的な登山の直前まで、休憩もせずに酔うまで酒を飲み、十分な登山用の装備も持たずに挑むとは、狂気の沙汰である。全員が無事に生還できて何よりである。次の機会があるとは思いたくないが、次に登山するときは、ある程度の情報は持っていたほうが安全であるということを学んだのである。
そんなことを考えているうちに、だんだんと意識が遠くなって眠りに落ちていった。
-
前の記事

第40話 DEATH SLIDING デス・スライディング〜死への滑走〜 2018.10.19
-
次の記事

第42話 復活 2018.12.22

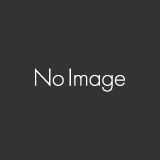







コメントを書く